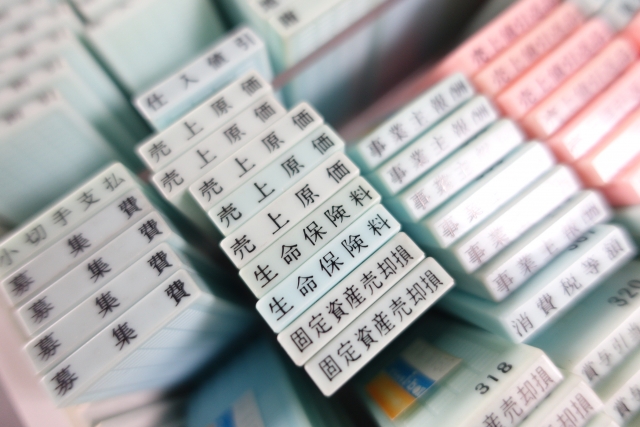個人事業主が自分で経理するとき「この勘定科目は何にするのかわからない!」と迷われたことはないでしょうか。
ボールペン1本買ったとして、“消耗品費”とするか“事務消耗品費”とするか。
ボールペン1本とコップ1つ買ったとして、すべて“消耗品費”とするか“消耗品費”と“事務消耗品費”に分けるか。
こういった線引きの難しい支払いをしたときは気にかかるところかもしれません。
特に、青色申告をする事業主にとっては悩ましい問題ですね。

勘定科目は厳密なルールはない
実は、勘定科目にはルール化されているものがありません。
たとえば、明らかに電話料金を“水道光熱費”などの勘定科目にするのは問題があります。
決算書を見たときに、大きな誤解を生じさせる科目の選択は避けるべきです。
という前置きをしたうえで、以下にポイントをあげてみます。
事業内容によって重要な支払いを分ける
たとえば歯科医師の例をとってみると、歯科技工士へ支払う技工料は“支払手数料”でもいいかもしれません。
一般的に“支払手数料”は銀行の振込手数料や専門家に対する報酬が含まれています。
しかしながら歯科医師にとって、技工料は売上に直接関係する売上原価を構成する大切な科目のはずです。
そのため“外注費”などの科目に分けてみるといいかもしれません。
このように自分の事業にとって重要な支払いを特別な科目に設定して分けるといいでしょう。
どのくらいの経費がかかっているのか、一目瞭然となります。
継続することで経営状態を知る
どのくらいの経費がかかっているのか一目瞭然となることによって、経営状態を知ることが可能になります。
同じ勘定科目の使用を継続することによって、前年との比較が可能になります。
・売上は上がっているのに利益が落ちているのはなぜ?
・どうすれば利益を出すことができるのか?
・前年と比べて何の経費が増えているのか?
・どの経費を省くことができるか?
このような経営状態の把握に役立ちます。
毎年勘定科目を変更すると、この変化がとらえられなくなります。
信頼の高い計算書をつくる
決算書を閲覧する利害関係者、たとえば取引先や銀行に対して、正しく経理しているとアピールするのに役立ちます。
損益計算書をみたとき、経費がすべて“雑費”だったらどうでしょう。
「経理がいい加減なのかな」と悪い印象を与えることになるでしょう。
やはり適正な経理をしている=経営状態を把握しているということは信用につながります。
家事費按分するものをまとめる
車を所有していると、ガソリン代、自動車税、自動車保険・・・など色々な種類の経費が発生します。
燃料費、租税公課、保険料・・・と分けても問題はありません。
しかしこれらの経費をすべて“車両費”とすると、確定申告の際にまとめて家事費を経費から減らすことが可能になります。
ひとつひとつの科目から車に関する支払いを集計しなおして、そこから何%削って・・・となると手間もかかりますよね。
科目をまとめることによって著しく経理処理がラクになります。
(まとめるのも適正な範囲が必要です)
気をつけなければならないこと
「勘定科目は厳密なルールはない」としましたが、注意点があります。
その年にすべて経費とすることができないものについては、固定資産として計上しなければならないということです。
1つにつき10万円以上(青色申告の方は30万円以上)のモノを購入した場合、その年にすべて経費とすることができません。
固定資産として貸借対照表に計上し、減価償却して少しずつ経費としていかなければなりません。
これは税法に定められたルールなので、これに関しては厳密な処理方法が存在します。
固定資産として貸借対照表に計上するための勘定科目が必要になるため、注意が必要です。